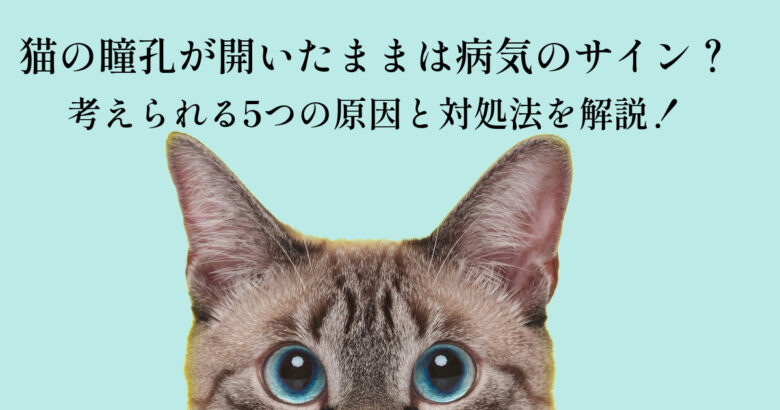猫の瞳孔が開いたままになっていることに気づいたことはありませんか?猫の瞳孔は病気以外にも光の量や周囲の環境によって変化したり、興奮状態や恐怖を感じたりするときにも大きく開きます。しかし愛猫の瞳孔が開いたままという状況は、飼い主としても心配になることでしょう。
そこで今回は、猫の瞳孔が開いたままになる原因と対処法について解説します。猫の瞳孔に違和感を感じる飼い主さん、ぜひ最後までお読みください。
目次
猫の瞳孔の役割は?

猫の瞳孔は虹彩の一部で、光の量を調節する役割を担っています。瞳孔が大きく開くと多くの光を取り入れることができ、暗い場所でもよく見えて、瞳孔が小さく縮むと、光の量を減らすことができるのです。
また瞳孔の開閉は瞳孔括約筋と瞳孔散大筋の働きによってコントロールされてて、瞳孔括約筋の働きで瞳孔を小さく縮めたり、瞳孔散大筋が働くと瞳孔を大きく開くことができます。
猫は夜行性動物なので暗い場所でもよく見えるように、瞳孔が大きく開くように進化してきました。そのため猫の瞳孔は、暗い場所では大きく開き明るい場所では小さく縮むという特徴を持っています。

猫の瞳孔の変化は人間よりもわかりやすく、変化を見つけやすいですね!
猫の瞳孔が開いたままになる原因5つ

暗い場所や興味のあるものを見ている
先にも述べましたが、猫は夜行性動物なので暗い場所では瞳孔を大きく開き、周囲の状況を把握します。そのため暗い場所で瞳孔が開いたままというのは「生理的な反応」であり、とくに心配する必要はありません。
さらに好奇心旺盛な猫は、興味のあるものを見ているときも瞳孔が大きく開きます。これは周囲の状況をよく把握するために多くの光を取り入れようとするための反応なので、心配はいりません。
興奮状態や恐怖・ストレスを感じている
猫が興奮状態や恐怖・ストレスを感じている時に瞳孔が開くのは、交感神経が興奮し「アドレナリン」という物質が放出されるためです。アドレナリンが放出されると、猫の瞳孔散大筋が優位に働き明暗に関わらず瞳孔が開いた状態になります。
薬の副作用
薬の副作用が原因で、瞳孔が開いたままでになることも。というのも通常の薬では滅多にありませんが、麻酔の後や交感神経を刺激する薬、副交感神経を遮断させるような薬を使うと、瞳孔が開いたままになることがあるからです。
もしそういった薬を使っているのであればその副作用かもしれないので、獣医師に相談してみましょう。
病気を患っている
瞳孔が開きっぱなしなのは、何かしらの病気の影響かもしれません。瞳孔が開いたままになる病気は主に眼の疾患だけかと思いきや、神経や内臓の病気が原因だったりもします。
いずれにせよ、病的な理由が原因であるなら早期の治療が必要なので早めに動物病院を受診してください。
猫の瞳孔が開いたままになる病的要因は?
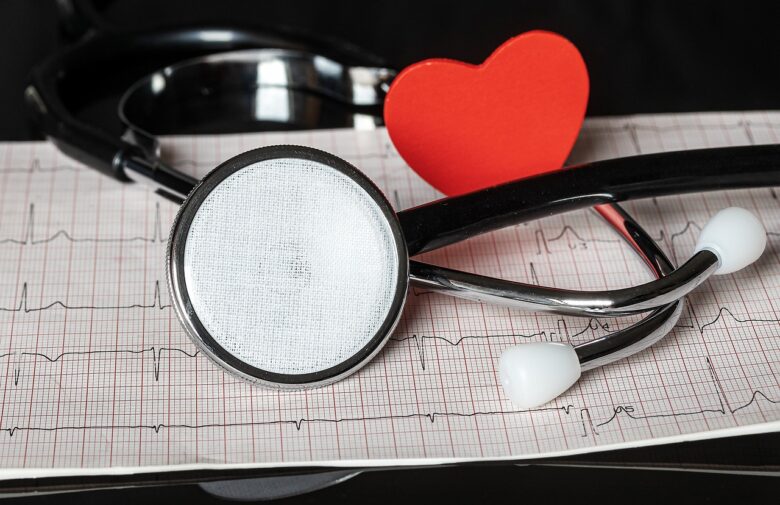
眼の疾患
緑内障
猫の緑内障は眼圧が上昇して視神経が圧迫され視力を失う病気で、緑内障を患うと眼がひどく充血し、瞳孔が開いたままになることがあります。
両目とも開いたままになることもあれば片方だけが開いたままになるケースもあり、症状が進行すると失明してしまう恐ろしい病気です。
ただ完治は難しいですが、眼圧を下げる薬などを使って進行を遅らせることができます。そのため瞳孔が開いたままだったり、白目の充血、角膜が青みを帯びるなどの症状が見られたら早めに動物病院を受診してください。
白内障
猫の白内障とは、目の中の水晶体が白く濁ってしまう病気です。水晶体は、目の中のレンズのような役割を果たしており、光を屈折させて網膜に焦点を合わせる役目をしています。
しかし白内障になるとその水晶体が白く濁って光を通す力が弱くなり、視力の低下・物にぶつかる・眼が白く濁るなどの症状があらわれます。
加齢や外傷や炎症、遺伝、糖尿病などの疾患が原因で、完治は難しい病気です。ただ点眼薬をつかって進行を遅らせることはできますし、水晶体を取り出し人工眼内レンズを入れる外科的手術を行うこともあります。
網膜剥離
猫の網膜剥離とは、眼球の後ろにある網膜が何らかの理由で剥がれてしまう病気です。網膜が剥がれてしまうと、電気信号が脳に伝わらなくなることで視力障害や失明を引き起こすことがあります。
猫の網膜剥離の原因は、高血圧・外傷・遺伝などさまざまです。初期の網膜剥離であれば、点眼薬や内服薬で網膜の剥離を抑える治療を行ったり、近年ではレーザー手術によって網膜を接着する治療も選択肢にあります。
瞳孔の開き以外にも、猫が眼を痛がる・涙が出る・充血するなどの症状があれば早めに動物病院を受診しましょう!
網膜変性症
網膜変性症は、猫の網膜が徐々に変性し視覚機能が低下する病気をいいます。進行性の病気であり、時間の経過とともに症状が悪化し、進行すると失明にいたる怖い病気です。
加齢や遺伝が原因ともいわれていますが、はっきりとした原因はわかっていません。また特定の治療法は存在しませんが、症状の進行を遅らせるためビタミンEやアスタキサンチンなどのサプリを服用することもあります。
瞳孔が開いたまま・暗い場所で見えづらい・物にぶつかる・物を目で追わないなどの症状が見られたら、早めに獣医師に相談してください。
そのほかの疾患
猫の瞳孔が開いたままというのは、なにも目の病気だけが原因となるわけではありません。次のような全身疾患が原因で、瞳孔が開いたままになることもあります。
甲状腺機能亢進症
猫の甲状腺機能亢進症とは、甲状腺から分泌される甲状腺ホルモン(サイロキシン(T4)、トリヨードサイロニン(T3))の分泌が過剰になる病気です。甲状腺ホルモンは代謝を活性化する働きがあるため、心拍数や体温・食欲・体重・毛並みなどに全身に影響を与えます。
猫の甲状腺機能亢進症の原因はほとんどが甲状腺の腫瘍(腺腫や癌)によるものといわれており、甲状腺ホルモンの分泌を抑える薬物療法を行ったり、手術で摘出したりして治療を行います。
症状としては甲状腺ホルモンの過剰分泌によって交感神経が優位に働くため、瞳孔が開いたままになったり、食べているのに痩せる、攻撃的になるなどが現れることが多いです。
慢性腎臓病
猫の慢性腎臓病(CKD)とは、腎臓の機能が徐々に低下し体内の老廃物や余分な水分が適切に排泄されなくなる状態が長く続いている状態の病気です。残念ながら機能が低下した腎臓はもとに戻らないため、症状は徐々に悪化していきます。
猫によくみられる病気で、とくにシニア猫やCKDのリスクが高いヒマラヤンやペルシャなどの猫は要注意です。
腎不全になるとそれが原因となって高血圧を引き起こし、網膜剥離を併発すると瞳孔が開いたままになって失明することがあります。早期治療が必要なので、もしCKDの症状がみられたら動物病院を受診しましょう。

動物病院でもCKDを患う猫は多くいました。シニア猫でよく見られましたが、4歳など若い猫も発症していることも少なくなかったっです。
脳や神経の病気
脳腫瘍や脳出血など、脳や神経に異常があるときも瞳孔が開いたままになることがあります。というのも脳や神経に異常があると、「目は見えてるけど瞳孔の大きさを変えることができない」状態になるというわけです。
脳や神経に異常が疑われる場合は、MRI検査をして内科治療や外科治療を行うことがあります。発作や痙攣、異常行動(壁に頭を押し付けたり、ぐるぐる回る)などが見られたら早めに獣医師に相談しましょう。
二次性高血圧
猫の二次性高血圧とは他の病気が原因で引き起こされる高血圧のことで、猫の高血圧の約90%が二次性高血圧といわれています。
先にも述べました慢性腎臓病や甲状腺機能亢進症といった病気が原因になることが多く、高血圧になって網膜疾患を患うと、瞳孔が開いたままの症状が現れます。やがて失明に至るリスクが高いので、早期の治療が肝心です。
猫の瞳孔が開いたままのときはどうしたら良い?

猫の瞳孔が開いたままというときは、早めに動物病院を受診しましょう。瞳孔の開きには生理的なものと病気が関係するものがあるといいましたが、素人が判断するには難しいです。
眼圧や涙の検査、角膜に傷がないかといった検査は基本的に日帰りでも行えますし、なにより獣医師に相談することで、早期発見だけでなく飼い主の不安を低減することができます。
そのため猫の瞳孔が開いたままで普段と違う様子もあれば、早めに動物病院を受診してください。

緑内障などは発症してから短期間で失明することもあります!目に異常を感じたらまずは動物病院に行ってください!
まとめ

猫の瞳孔は光の調節を行う重要な役割を果たしています。瞳孔が開いたままというのは生理的なものから病的な理由などさまざまで、安易に考えるのはいけません。
瞳孔の変化は猫の健康状態を示す一つのサインともいえるので、もし愛猫に異常を感じた場合は早めに獣医師へ相談することが重要です。