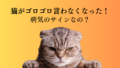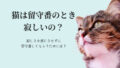オス猫を飼育していると、ある日大きな声を出したり臭いの強い尿をまき散らしたりする行動を目にしたことがありませんか?実はこれ、発情期を迎えたメス猫に誘発されてとるオス猫の発情行動です。ではこの行動をする、オス猫の発情期の期間はいつから・どのくらいするのでしょうか…?
そこで今回はオスの猫の発情期の期間・問題行動とその対策・去勢手術について紹介していきます!オス猫と暮らしている飼い主さん必見の内容です。
目次
オスの猫の発情期の期間は?

オス猫に「発情期」はない!
まず知っておきたいことは、オス猫に「発情期」はないということです。というのも猫の発情期というのは、メス猫が交尾できる状態に相手を探し求める期間のことをいいます。
オス猫は性成熟すればいつでも交尾可能状態であり、ある特定の時期だけにメス猫を求めることはありません。したがってオス猫には明確には「発情期」というものがないのです。

「発情期」を迎えるのはメスだけ!オスは発情期のメスによって発情をしますが、オスそのものに交尾ができる期間(つまり発情期)はないのです!ややこしいですね。
基本的にヒト以外の哺乳類は、発情期以外で交尾することはありません。またオスも発情期を迎えていないメスには反応しないといわれています。
オス猫が発情するのはメス次第だが、約4~10日
オス猫の発情の明確な期間はありませんが、4~10日ほどです。これはメスの発情期間と同じで、この時期のメスが発するフェロモンや鳴き声に誘われてオス猫は発情するからです。つまりオス猫の発情はメス猫によるというわけです。
なおいつでも交尾可能とはいえ、発情期のメス猫がいない限りオス猫も発情を誘発されることはありません。またオス猫は去勢しない限り、発情期のメスがいれば15歳くらいまで発情するといわれています。

平均寿命の年齢になったとしても、発情するなんてすごい…!
オスの猫の発情期の期間はいつから?

オス猫が発情するようになるのは、性成熟を迎える生後6か月~12か月ごろです。しかし早ければ3ヵ月頃にはマーキングなどの行動する猫もいるようです。

わたしの愛猫は4ヵ月ごろからマウンティングを始めていました…。
また始まる季節については、メスの発情期に合わせた春(2月~4月)と夏(6~8月)に見られます。しかし初秋までメスの発情期が続いていれば、それに伴いオス猫も発情します。
オスの猫の発情期の期間に見られる行動
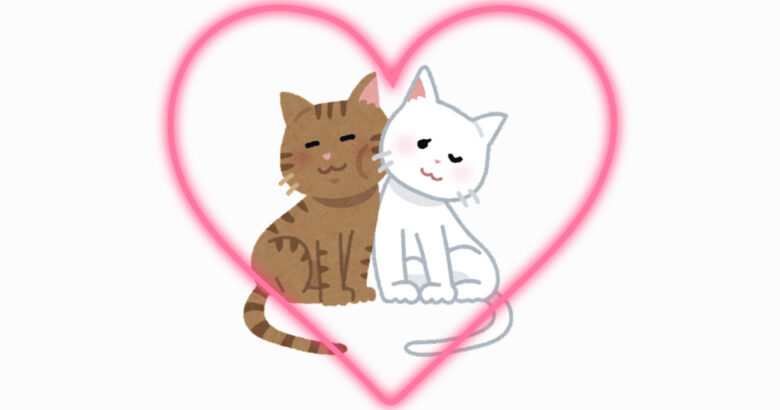
発情を迎えたメス猫に誘われて発情したオス猫には、次のような行動がみられます。そしてこれらの行動は、多くの飼い主を悩ませているものです…。
マーキング(スプレー尿)
マーキングは、少ない量の尿をしっぽを立てた状態で垂直面に噴射することで、スプレー尿ともいわれます。この尿は通常の尿とは異なりとてもキツイにおいがするのですが、この臭いで縄張りを主張したりメスをおびき寄せたりするのです。
家の中では新しい家具や自分の通り道に尿を噴射する傾向があります。一度臭いを付けられるとなかなか落とすことができないので、多くの飼い主が頭をかかえている行動です。

我が家では愛猫が去勢手術前日に突然わたしの布団の上にスプレーしました…。何度か洗いましたが結局臭いは取れず破棄しました…
大きな声で鳴く
オス猫は発情するととても大きい声で鳴くことがあります。個体差はありますが「ナ~」や「ニャ”ー」など低く重い声で鳴いてメス猫を誘うのです。日中鳴いている分にはまだマシなのですが、夜に鳴かれると睡眠を妨げる原因になったりもします…。
マウンティングをする
マウンティングとは、オス猫がメス猫にのって交尾をする体勢を指します。視界にメス猫がいなくても、漂ってきた臭いを感じ取ってマウンティングをする猫も。人には全く感じ取ることはできませんが、猫同士では感じ取ることができるのです。

我が家の愛猫は、どこからかメス猫のにおいをキャッチして毛布に一生懸命マウンティングしていました…(笑)
落ち着きがなくなる
メスの発情期には、オス猫もどこかソワソワした行動をとることも。メス猫を探している行動ですが家の中にはメス猫はいないので、長い時間ぐるぐる探し回る猫もいるようです。
攻撃的になる
オス猫は発情期のメス猫をとられないように、他の猫や場合によっては飼い主にまで攻撃的になることがあります。これは本能的な行動なので、やめさせられませんので、攻撃的になった猫には近づかない&ほかの猫と隔離するなど基本的に「避ける」ようにしましょう。
オスの猫の発情期の期間にとる行動への対策は?

オス猫の困った発情の行動…。これを解決するための方法は基本的にはありません!というのも、これらの行動は猫の本能的なものなのでやめさせることができないからです。そのため、解決するには去勢手術のみ。それ以外ではあくまでも「対策する」にすぎません。
スプレー尿には「ペットシートを敷いておく」
猫のマーキング(スプレー尿)に困ったときは、スプレーしてしまう場所にペットシーツを貼っておきましょう。猫は同じ場所にスプレーする傾向があるので、猫の行動を観察して対策するとgood!
多頭飼いならほかの猫と離す
もしも同居猫がいる場合は、発情するオス猫とは隔離しておきましょう。先述しましたが、攻撃的になっているかもしれないため、ほかの猫を傷つけさせないようする必要があります。またあたりまえですが、同居猫に中に未避妊のメス猫がいる場合は子猫を望まない限り隔離は必須です。
外が見えないようにする
オス猫の発情は、発情中のメス猫につられて起こるもの。そのためメス猫が発情する期間は、カーテンなどを使って外が見えない工夫をするのがおすすめ。完全に防止することは難しいかもしれませんが、発情はしにくくなります。
日中はたくさん運動させる
夜鳴きを抑える意味でも、日中はたくさん遊ばせて夜間はぐっすり寝てもらうのがgood!たとえばレーザーポインターやラジコンねずみなど、たくさん体を使えるおもちゃがイチオシです。1回10~20分の遊びを、1日2~3回くらいしてみてください!
去勢手術をする
オス猫の発情行動を根本的にやめさせたいのであれば、去勢手術をしましょう。去勢手術は、オス猫の精巣を取り除き男性ホルモン(エストロゲン)の分泌を抑えるための手術です。この手術を受けさせると、男性ホルモンの分泌量が大幅に減少するため、発情の行動もほとんど見られなくなります。

去勢手術は子猫を望まないならぜひしておきたい手術!後の見出しで詳しく紹介します!
オスの猫の発情期の期間にやってはいけない飼い主の行動は?

オス猫が発情しているときは、飼い主も接し方に注意が必要です。次のようなポイントをおさえて猫に接しましょう。
叱る
発情しているオス猫に叱る行為はNG!何度も言いますが、発情行動は猫の本能的な行動。なのでしつけをしたらやらなくなるということはありません。
反対に、叱れば猫にストレスをかけ逆効果になりますし、信頼関係が傷つくこともあるので絶対にやめましょう。発情行動の対策は先述したような、「飼い側が発情行動をできない環境づくり」をするしかありません。
構いすぎる
発情中のオス猫を構いすぎるのも控えましょう。特にマタタビはやめた方が良いです。
というのも発情中のオス猫は興奮しやすく、マタタビなど猫の気分がハイになるものを与えると発情行動がさらに悪化したり、攻撃的になったりすることがあるからです。一時的にしのぐことはできますが、それで行動を抑えることはできないのでなるべく控えるのがベター。
オスの猫の発情期の期間をなくすのに「去勢手術」とは?

去勢手術とは、オス猫の精巣を切除しテストステロンという男性ホルモンの分泌を抑え、望まない妊娠を避けたり発情行動などオスならではの行動を抑制するために行う手術です。
これにはほかにもさまざまなメリットがあるため、オス猫はぜひ受けておきたい手術といえます。
去勢手術の必要性は?
オス猫の去勢手術の必要性はあります。というの去勢手術にもデメリットはありますが、それよりもメリットの方が大きいからです。
子猫を望まず、発情時の行動をどうにかしたい!と思っているなら去勢手術を検討すべき。そしてもし行うのであれば、猫が発情する前の早い時期がおすすめです。猫の体格にもよりますが、生後半年~手術を行える病院がほとんどなので、ちょうどそのくらいに去勢手術ができると良いでしょう。
もちろん発情経験があっても去勢手術は効果的です。ただ男性ホルモン量は個体差があり、去勢をしてもまだ発情行動を続ける猫もいます。とはいえ多くの猫は発情行動がなくなったり、その頻度やメス猫への関心自体が薄れる傾向があるので、効果は高いものです。

愛猫は去勢手術をしても数か月間はマウンティングをしていました…。しかし半年も経つころには、発情行動はみられなくなりました。
去勢手術のデメリット
去勢手術には次のようなデメリットがあります
全身麻酔のリスク
猫の去勢手術は全身麻酔をかけての手術にるため、そのリスクはゼロではありません。とはいえ、持病や肥満などの疾患を持っていなければトラブルの可能性は高くありませんが…手術前にはしっかり獣医師と話すようにしてください。
子孫は残せない
あたりまえですが、去勢手術をすると子孫を残すことができません。去勢手術は猫の精巣(精子をつくる器官)を取り除く手術なので、生殖機能を失うということになります。
肥満のリスクが上がる
猫は去勢手術をすると肥満になりやすい傾向があります。というのも、去勢手術により性ホルモンの分泌は大幅に抑制されることにより、食欲は増加し運動量は低下してしまうからです。そのため去勢手術後は適度な運動が大切なポイント。

怠けものの愛猫は去勢後体重がどんどん増加して、足長マンチカンですが、体重6㎏を超えてしまいました…。
去勢手術のメリット
去勢手術を行うメリットは次のようなものがあります。
発情時の行動を抑えることができる
去勢手術を行うと、先ほど紹介したような発情時の困った行動を大幅に減らすことができます。なかには完全に発情行動をしなくなる猫もいるほど。これは精巣を切除することにより、発情行動を引き起こす性ホルモン(テストステロン)の分泌が抑制されるためです。
生殖器官に関係する病気の予防ができる
去勢手術を行うことは、生殖器官の病気を予防するのにも効果的。生殖器官の病気というのは、たとえば前立腺の病気や精巣にできるガンなどがあります。
これらの病気を治すためには手術が必要となるケースが多いですが、とくにシニア期を迎えた猫には体への負担が大きいもの。そのため病気の予防を行うといった観点でも、去勢手術を選択する飼い主さんもいます。
望まない妊娠を避けられる
去勢手術は生殖機能を失うことになりますが、同時に望まない妊娠を避けることができます。オスは妊娠しませんが、野良猫やよそのメス猫を妊娠させてしまったら大変です。
たとえ室内飼育とはえ、脱走のリスクはゼロではありません。そのため特別な理由がない限りは、去勢手術を受けることをおすすめします。
まとめ

今回はオス猫の発情の期間を中心に、発情時の行動やそれの抑え方、また去勢手術までを解説してきましたがポイントは次の通りです。
- オスの猫の発情期の期間は約4~10日だが、メス猫による
- オス猫には発情はあっても、「発情期」はない
- オス猫は発情するとマーキングや大声で鳴くなどの問題行動をする
- 問題行動はやめさせられない。基本的にできない環境をつくらせるしかない
- 問題行動を抑制させるには、去勢手術が最も効果的
オス猫は基本的にメス猫の発情期に合わせて発情が誘発されます。そのため具体的な発情の期間は、メス猫の発情状況によって異なってくるのです。
この記事を読んでいる人には「愛猫の困った発情行動、いつまで続くの!?」と思っている人もいるでしょう。もしそのような思いを持っているなら、ぜひ去勢手術を検討してみてください。子猫を望まないのなら、効果的でとても良い選択肢となるでしょう。